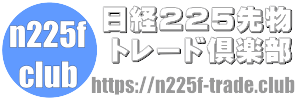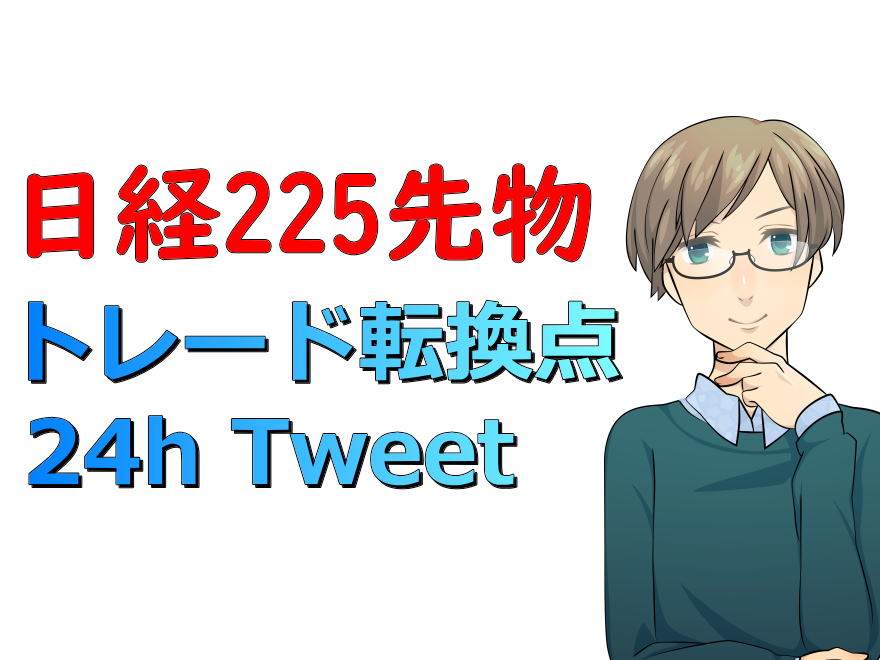2025年4月14日
スティーブン・ミランの論文と米国経済政策の方向性
【考察】
スティーブン・ミラン氏は現在、トランプ政権下で大統領経済諮問委員会(CEA)の委員長を務めており、経済政策に関して大統領に直接助言を行う立場にあります。彼の発信する意見や分析は、政策決定に影響を及ぼす可能性が高く、注目されています。
そのミラン氏が執筆した「国際貿易システム再構築のユーザーガイド(A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System)」が、マーケット関係者の間で大きな関心を集めています。
この論文のポイントは次の3点に整理できます。
(A)米ドル高と貿易不均衡の構造的問題
ミラン氏は、米ドルが世界の準備通貨として過度に評価されていることで、アメリカ製品の価格競争力が損なわれ、製造業の空洞化が進み、国内に経済的不満が蓄積していると指摘しています。このような状況が貿易赤字や雇用流出を引き起こし、保護主義的な声の背景になっていると分析しています。
(B)関税政策の活用可能性
彼は、関税を単なる税金ではなく、政策ツールとして捉えるべきだとしています。特に、2018〜2019年の対中関税措置を例に挙げ、関税が為替レートに影響を与える「通貨オフセット効果」をもたらしたと評価。これにより、ドル高による不利な条件をある程度緩和し、インフレ抑制と貿易赤字縮小の両立が可能になったと説明しています。また、アメリカ市場へのアクセスを「特権」として扱うことにより、関税を外交交渉の武器として使う発想も示しています。
(C)通貨政策を含めた多角的アプローチ
関税に加え、外国為替市場への介入や、連邦準備制度(FRB)による金利政策の調整なども選択肢として検討されています。これらの施策が金融市場に与える影響、とくにボラティリティ(価格の不安定化)への注意を促しつつ、段階的な実施や市場との丁寧なコミュニケーションが重要であると述べています。
【その他の考慮点】
この論文において特に重要なのは、ミラン氏自身が「これは政策提言ではなく、考え得る政策オプションの分析である」と明言している点です。目的はあくまで、経済や金融市場への影響を見極めるための枠組みを提供することにあります。
また、関税政策の実行にはリスクがあることも認めています。たとえば、報復関税や物価上昇といった短期的なマイナスの影響が想定されますが、それでも「適切に管理すればアメリカ経済の競争力を高めつつ、消費者への影響を最小限に抑えられる」としています。
【全体的なまとめ】
この論文は、トランプ政権が進める相互関税政策に理論的な根拠を与えるものとして読まれています。特に、米ドルの是正に向けた動きは、通商政策の枠を超えて金融政策にも及んでおり、今後の為替市場・金利動向にも影響を与える可能性があります。
市場関係者、とくにトレーダーの視点から見ると、関税政策そのものよりも、為替介入や金利調整といった周辺政策の実行可能性とタイミングのほうが、短期的な相場に与えるインパクトが大きいといえそうです。
【用語解説:初心者向け】
・大統領経済諮問委員会(CEA)
アメリカ大統領の経済政策に関する助言を行う専門機関で、経済学者などがメンバーになっています。
・準備通貨
各国の中央銀行が外貨準備として保有する通貨のこと。米ドルが代表的で、世界の貿易や金融で広く使われています。
・通貨オフセット効果
ある政策(例:関税導入)が通貨の価値に影響を与えることで、輸出入のバランスが間接的に調整される現象を指します。
・外国為替介入
政府や中央銀行が通貨の売買を行い、自国通貨の為替レートに影響を与える行為です。
・連邦準備制度(FRB)
アメリカの中央銀行にあたる組織で、金利の調整や市場への資金供給などを通じて、経済の安定を図る役割を持っています。
・ボラティリティ
価格変動の大きさを示す指標で、数値が大きいほど相場が不安定であることを意味します。